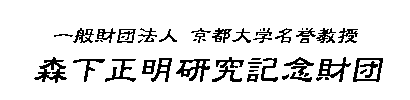戦前・戦中の昆虫研究室と私
京都大学 1935(昭和10)年卒 森下正明
私は中学時代から昆虫を集めたり、ファーブル昆虫記を読んだりして、無性に昆虫が好きになっていた。旧制高校(高知)の一年先輩には後に玉川大学で蜜蜂の研究をされた岡田一次さんがおられて、その頃から補虫網を持って歩いておられるのを遠くから畏敬の眼を持って眺めてみたものである。高校卒業後は昆虫を専門にやれる大学をえらぼうと決心して、あちこちの大学の履修科目などを調べるうち、京都大学の農学部農林生物学科の履修科目には直接昆虫学に関係する科目はもちろん、その他理学部の動植物科目が多く入っているのに気を引かれた。その上ここでは、それまで入学試験があったことがないという、現在では考えないことが一番の魅力であった。高校時代の私は数学が苦手で落第点ばかりもらっていたから、もし入学試験があったら合格はまず望み得なかったからである。幸い定員10名に10名の志願者で、昭和7年、無試験で無事入学することができた。
1回生のうちは助手の山田保治さんについて昆虫学の実習を行ったり、昆虫を集めたりしたが、2回生になって昆虫学教室に配属され大部屋の中に席を与えられた。この部屋(部屋番号252号室で、後に昆虫会同窓会名を252会と名づける事になった)には岩田久二雄、可児籐吉さんを始め、岡崎、野田の諸先輩がおられたが、皆親切で私たち(小田柿、柳田と私)新米も気楽にさせてもらった。なお、助教授の徳永雅明さんや助手の西川満三郎さん、山田さんはもちろん別部屋で毎日顔をつき合わせるほどのことはなかったが、それでも何かと気を配っていただいたことをおぼえている。誠に居心地のよい研究室であった。
今西さんはすでに理学部へ移っていられたが、こちらにも嘱託という名儀で席があり、たまには顔を見せられることがあった。私はファーブルの影響もあってハチの生態を調べたいと岩田先輩に相談を持ちかけたところ、「ハチは自分がやっているから君はアリをやれ」ということで、アリの生態を調べることになった。私は子供時代から試験管に大きいアリと小さいアリを入れて喧嘩させたり、アリの行列を観察したりしており、ファーブルの昆虫記を読むようになったのもアリの奴隷狩りの記述の部分でたまたま眼にとまったのが機縁であったから、よほどアリに縁があったと思われる。ところが研究を始めようにもまずアリの名前がわからない。日本昆虫図鑑にはアリはほんのわずかしか載っていないので、ヨーロッパの検索表を引っ張り出してきたり、外国人の書いたアリの原記載をさがし出してタイプを打ったりして苦労させられた。幸い大阪に寺西暢というアリの研究者がおられたので、ときどき出かけては名前を教えてもらった。私ばかりでなく戦前の若手のアリの研究者は大なり小なり寺西氏に教えを請うており、現在の日本のアリ類研究の基礎はその後の訂正や発展はあるもののほぼ寺西氏によってつくられたと言える。
同級生に山歩きのすきな小田柿進二君がいたので二人でよく山へ出かけた。また可児藤吉さんや今西さんとも山歩きを行った。そしてその内にアリを材料とした垂直分布帯を明らかにしたいというのが私の念願になった。可児さんと出かけるときは渓流沿いでは私が一服している間可児さんが忙しく、尾根道では私がアリ探しをしている間可児さんは適当な所で腰を下ろしてスケッチなどしているといった具合であった。 山行の合間には大学の植物園でアリの観察に励んだ。指導教授の湯浅八郎先生は毎週1回、その週にやったことを報告するよう求められた。わたしはいつも話す種が割合多くあったので、報告日もそれほど苦にならないですんだ。クロヤマアリの観察中、このアリの寄生蜂を見つけその生活史も調べることになったが、その時先生はわざわざ植物園まで来て一緒に産卵行動を観察されたことを覚えている。
その頃今西さんの提案で昆虫学研究室の若手全員で西賀茂の動物相の調査をしたことがある。河原、クヌギ林とか、松林とか各種植生の場所に10数個の方形区を作り、月に一回その方形区にいた虫を採取記録するという仕事を一年を通して行なった。しかし、調査をしても昆虫以外のいろいろの小動物や、昆虫でも幼虫類が多く、なかなか名前がわからない。それがこの共同研究をまとめることができなかった大きい理由でもあったが、その当時としては大へん野心的な仕事であったといえる。それにたとえ形にはあらわれなくても、私たち初心者にとってはこの体験によって得たものは極めて大きかった。
その当時は徐々に日中間の戦争が拡大しつつあった頃で、研究者の間には軍隊からの召集がいつくるかわからないという不安があった。召集されるまでに少しでも仕事をしておきたいというのが恐らく多くの研究者の気持だったであろう。私は昭和10年に大学を卒業してすぐ無給副手にしてもらいしばらくは親からの仕送りで頑張ったが、いつまでもというわけにも行かず、と言って大学を離れるのも残念であった。幸い昭和12年立命館商業学校の教師の口があって、勤めながら研究を続けることができた。この学校では授業の時間以外は自由であったので、できるだけ授業時間をかためてもらって、あいた時間は大学へ出かけた。大学では私は副手の身分のままで席もそのまま与えてもらっていたのである。この副手という制度は実に便利な制度で、大学院生のように月謝はいらない、無給ではあるが旅行する際は学生と同じく内地では2割、旧満州や朝鮮など外地ではたしか3割の鉄道違賃の割引があって、大いに助かった。立命館商業部ではグライダー部の面倒も見てほしいとのことになって、夏休みに甲府飛行場まで指導者の講習会に行き、2級滑空士の免許まで、取ることができた。案外この方面の素質が私にはあったらしい。おかげで学校では免許を持った人を特別に雇うことがいらなくなり、私の給料も上がったのはよかったが、生徒に対する毎週一回の滑空訓練をせまい運動場でやらねばならず、事故を起こしはしまいかと毎回ヒヤヒヤものであった。
大学ではそのころすでに湯浅先生は同志社に移られて後の教授がどうなるかということが問題になっていた。全国のあちこちに散らばっていた昆虫出身の先輩諸兄に集まってもらって後任教授に誰がよいか討論し、最後にはわれわれ新米まで含めて投票したが、その結果今西さんが最高点になった。そこでこの結果を教室の主任教授に誰かが持って行ったように思う。この時代は今と違って若い連中がいろいろ言つても通る時代ではなかったが、投票までやったのは画期的なことだったと思う。しかし予想したことではあったがわれわれの希望はかなえられず寺川忠吉教授が就任されることとなった。 もっともこの会議では寺川先生の名も話題に上っていたから、あるいは第2位になっていたかもしれない。寺川先生が初めて教室に入られた時ヤンチャ坊主どもが並んでお迎えしたが、先生もうるさい連中がたくさんいると思われたと思う。先生は農薬など農業害虫を相手にした仕事を若い連中にさせたいと思っておられたに違いないが、特に研究テーマを代えよとかいう指示は何もなく、勝手なことをやらせて頂いたのは有難いことであった。
昭和14年になって医学部の衛生学の戸田正三という先生が興亜民族生活科学研究所というのを学内に作って、動物では今西さん、植物では三木さんが所員となった。私は今西さんから助手になって蒙古旅行に行かないかとさそいを受け、立命館商業を辞職し、2人で大陸の馬車旅行に出かけた。そしてそれ以後、昭和16年のミクロネシアボナペ島調査や昭和17年の北部大典安嶺探検など、戦前・戦中を通じて今西さんと行動を共にすることになった。そのうち昭和19年になって、大陸の草原地帯の自然と文化の研究のため西北研究所が今西さんを所長として発足することになり、私もその一員として蒙古高原の入口にある張家口に腰をおちつけることになった。しかし昭和20年の4月、同僚の中尾佐助氏とともに現地召集を受け、はるか西の山西省で兵隊生活を送るはめになった。そして8月に終戦、10月にやつと召集解除になり、どうやら天津までたどりついて張家ロから引き揚げてきていた研究所の人たちと合流し、12月に日本に引き揚げることができた。
前に述べたとおり、高等学校時代数学が不得意だったので、大学に入り昆虫研究に専念できることになった時は、これで数学とは緑が切れたと天にも登る心地であった。しかし実際に仕事をしていると数学を多少でも使わないと不自由を感ずるようになった。池の水面で活動するヒメアメンボの観察をしていると、まず分析の問題がでてくる。コードラートをとって分布を調べるやり方はあるが、一つの池の中に10やそこらの個体数しか見られない場合はどうにもならない。自分自身で新しい方法を考えねばならないという場面に直面した。特に動きを考えるとなると動いた距離を測らねばならないし、また空間分布というのも見方を変えると個体間の距離の関係でもある。従って距離を測るのが分布の本質を表現するのに一番よい方法ではないかとの素人考えで生み出したのが間隔法である。 もっとも数学に弱い私には直接平面上の分布までは手が出せず、線分への投影点の分布間隔といった、まどろっこしい方法で満足せざるを得なかった。この研究は立命館に行く直前から直後にかけての昭和12年に実際の仕事をしてひとまず論文を書き上げていたが、出版できなかったので原稿のまま終戦後まで放置してあった。さて終戦になり中国から引き揚げて嵯峨高女、さらには鴨沂高校で教えるうち、私は病気で動けなくなってしまった。病床にあって私は、これから先どんな仕事ができるだろうかと考えた。戦前戦中を通じて努力してきたアリの分布調査の結果などはごく一部を論文として発表しただけで、残りのノートの大半は大陸に置いてきてしまい、まとめようにも今はほとんどゼロである。身体さえ達者ならまた調べ直すことができようが、この病気ではもし治ったとしても山登りなどはおぼつかない。しかし考え直せば、大陸から無事に帰れただけでももうけもので、ぜいたくは言えない。とりあえず今まで敬遠してきた数学的取扱いなら寝たままでもできるだろうから、まずこれから始めようと決心し、数学書を枕元に置いて、前に手がけた間隔法をもう少し一般化することを試み、起きられるようになってからはクロバ工やアリジゴクを使った実験をやりながら環境評価の理論化を考えた。後になって「森下はころんでもただでは起きない」などと人から言われたが、私としてはただできることをやってみようとしただけのことである。なお私が病床にある間、教え子の鴨沂高校の生物研究会の生徒たちが、毎日交替で九条山の上の私の住居まで見舞いや手助けに来てくれたのは何と感謝してよいかわからない。 (生徒達とは、大谷大学名誉教授・日下部有信先生、京都大学名誉教授・辻英夫先生たちである:管理者追記)
さきに述べたアメンボの原稿は私が中国へ行く時日本に残しておいたので無事であったが、私が京都へ帰つてから理学部動物教室の研修員にしてもらいながら寝こんでしまったので、これを報告書代りに宮地先生に見て頂いた所、思いがけず学位論文にせよと言われた。そこであわてて新しく拡張した間隔法やいくらかの数学的吟味をつけ加え、それに多少の新しい文献の追加も行なって正式に提出した。思えばもしこの時学位をもらっていなかったら間もなく新設された九州大学生物学教室の生態学講座に職を得ることもできなかったであろうから、その後私がこの新しい環境で研究を続ける時間的余裕を持ち得たのは全く宮地先生のお蔭である。
さて病気をしてからは山へは登れなくなり、一度はあきらめかけたアリの仕事であるが、その後もアリとは縁が切れなくて、旅行するたびにアリを採取し分布を調べている。そのうちにアリ類研究会という会が、できて現在私が会長をしているが、この会は非常に楽しい会で、「アリ類」という会誌を出しているのと、毎年一回、2泊3日かけて研究会を持ち、うちl日は採集会をやっている。優秀な若者も育っていて頼もしい。
さきに述べた可児藤吉さんは、その後召集を受け、サイパン島で戦死された。戦後現された原稿の一部を「木曽王瀧川昆虫誌」として私は整理出版したが、その後残りの原稿や既発表論文も加えて「可児藤吉全集」(全一巻)が渋谷寿夫氏等の努力で思索社から出版されている。可児さんは初め医用昆虫学を志し、卒業論文の「ノミの触角について」から続いて川の中のブユの分布調査を行ったが、後にカゲロウやトビケラなど水棲昆虫全般の分布にまで研究の範囲を広げた。この当時の彼の悩みは川の上流から下流までの河川型の表現法についてであり、私も下流の上とか山地性平地流とか妙な表現法を助言したことをおぼえている。しかし可児さんは最終的にはA、B、Cの大文字と小文字の組み合わせで簡潔に河川型を表現する方法を立案した。彼はよい人柄で、真面目であり、絵を書くのが上手で、非常に丹念な仕事をされた模範的な研究者であったと思う。その当時でもすでに川の生態学を彼ほど深く研究した人は世界でも恐らく数少なかつたであろう。全く惜しい人をなくしたものである。
1987年(昭和62年)7月27日京大農学部昆虫学研究室の一室で、伊藤五彦氏とともに森下正明氏からお話をうかがうことができた。その時の内容を前田がまとめたものを先生に訂正していただいた。森下先生に厚く御礼申し上げるとともに、同席下さった伊藤氏に感謝する。語の中で、数学に達者な先生が高等学校時代に数学が最も不得意だったと聞かされて全く驚くとともに、九大、京大での先生のその後の研究の発展を合わせ考えると大きな感銘を受けた。(前田 理記)