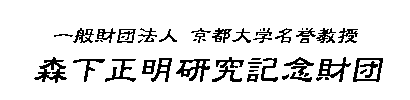森下先生の思い出
森下先生の思い出
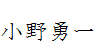
九州大学時代の森下先生の思い出
京都大学では先生も先輩もすべて「さん」づけである。京都から九州大学に森下助教授が赴任して直後からしばらくの間は森下さんにつれられてしばしば京都大学に行き、同大の学生と共にセミナーを受けることが多かったが、その際に私たちが「森下先生」とよぶと、向こうの学生たちから笑われた。学の先達という意味からは「さん」でいいのだ、と言うわけである。心理的に上長や先達を先生とよぶ風習にあった九州のわれわれとしては何とも消化不良の呼び方に感じられた。「さん」と呼ぶか「先生」と呼ぶかというのは日本の社会的な習慣であり、どちらでもよいような感もあるが、私にとっては学問的に人生経験の豊かさにおいてもまさに「先生」であり、何の衒いもなく「森下先生」であった。
もっとも、だんだん年を経てこちらも多少は人生経験をつんでくると、ときには「森下さん」と呼びかけることもあり、仲間うちではもっぱら「さん」づけであった。
以下の文章ではその場その場で適宜使い分けることにする。
- アリジゴクのこと
九大に赴任した当時(昭和27年)はまだ40台ぎりぎりで才気煥発の森下さんであった。私も昭和25年九州大学入学であるので、三年生で講座配属の直前であった(当時の九大理学部生物学科では3年後半から自分の希望の講座に出入りし、適否を自己診断して、4年生から卒論のための講座を決めるという制度であった)。その頃「生物の行動を測り出す」という言葉を森下先生からよく聞かされたものである。私はその「測る」という言葉の新鮮さにつられて講座入りをきめた。
赴任当時の森下さんは「ヒメアメンボ」の学位論文が高い評価を受け、「生物から見た環境評価」という考えを理論的に一般化しようという意欲に燃えていたように思う。これらの考え方は森下正明生態学論集(第一巻)の序文からも読み取れる。
九大で森下さんが最初に始められたのはアリジゴクの巣の分布様式と砂にたいする嗜好性の研究であった(もっとも、その研究は京都で療養中にもすでに着想があったようで上記アドレスの中の大谷有信さんのメッセージにも述べられている)。
私たち3,4年の学生は実験の見習いとしてアリジゴク集めをさせられた。周知のようにアリジゴクは昔風の墓地の砂地や砂海岸松林の倒木のや、傾いた幹の下側などにすり鉢状の巣を作って潜んでいる。それを求めて箱崎の周辺はおろか遠く西新や姪浜までチンチン電車で出向いた(なぜか博多の西の方ばかりで東の方の記憶が無い。香椎以遠はササで覆われていたためであろう)。
採集はピンセットと小さな管ビンをボール箱に詰めたものが道具である。管ビンは径1センチ、高さ3センチで採集時に砂を少々とアリジゴクを1匹だけ入れる。数匹一緒にすると共食いをする。幾人かの組が同時に出かけて研究室に持ち帰る。先生に成果を渡すと、先生はそれをあらかじめ砂を敷いた広い箱の中にぶちまける。このときのぶちまけ方は先生流のやり方であり、学生にはさせなかった。そのわけは後にアリジゴクの分布と関連したことであることが後に分かった。
アリジゴクはご存じのようにウスバカゲロウの幼虫である。砂地にスリバチ状の穴を掘り、地上を徘徊するアリやその他の昆虫類をなかに落として捕食する。穴に落ちたアリなどはスリバチを這い上ろうとするが砂が崩れて上れない。ジゴクの方も大顎を振り回して砂を餌動物にかけて落とそうとする。落ちてきた餌は大顎に挟んで砂の中に引きずりこむ。この大顎から消化液を餌の体内に注入し、消化した組織液を餌として吸引する(体外消化)。従ってアリジゴクは蛹化するまで糞をしない。
森下さんは馬場金次郎さんの著書などで得た知識をもとに九大前の喫茶店(店名プランタン、通称門前屋)で時間を忘れてこれらのアリジゴクなどの蘊蓄をかたむけられ、同時に夢を語られたが、それを書くと長くなるので割愛する。
こうして得たアリジゴクを森下式実験に供するわけである。実験用の砂を入れる箱は上等の菓子を入れるへぎ折りの薄板(大谷記事参照)であり、実験目的に応じた大きさにこれを折り曲げ、角を小釘やホッチキスで留めてあった。当時の研究室にはところ狭しとへぎ折りの箱が積み上げられていた。その隙間に砂の山があり、学生たちがその砂を粗い、中間、細かいの三段階に篩い分けていた。まわり中が砂埃で、当時助手をしていたKさん(かれは森下さんの仕事には一切手を出さなかったし、興味も無かったようである)はきたないきたないと言って自室の扉を恒に固く閉ざしていた。「環境密度論」(環境評価論ともよぶが、生物の目でみた環境の好悪をその行動を通じて人間が測り出す、という意味である。近年の環境影響評価とごっちゃにされないことを望む)はこのアリジゴクの実験によることは先生の論文を参照されたい。
森下さんの個体の分布論はヒメアメンボに端を発し、アリジゴクで動物の実態を知り、それらを元に理論的展開をしたのである。2)「天然」のランダム分布
サイコロを何回もころがして、各回毎に出た目を記録する。その数字を書き並べたものがランダム数列である。現在では計算機にランダム計算法が組み込まれているので乱数と入力すれば、即、乱数が発生する(但し、これは疑似乱数)。森下先生はアリジゴクの研究以来生物個体群の分布様式の解析を目指した。
生物個体群の分布様式(分散様式)を研究する場合、個体の分布図を作るか、野外で直接に方形枠を紐などで引いて、方形区当たりの個体数を数えて、分布の型を調べるのが普通である。MorisitaのIΔなどはたいへん広く使用されている。これから紹介しようという話はIΔなどが開発されるまでの最初のステップにかかわる逸話である。
野外個体群を対象にしている研究者はたいてい知っているが、自然界では生物個体は普通は集中(かたまり)分布をしている。個体分布を方形区で区切って、枠内個体数を数える場合に集中(塊)と枠の直線とが交差することが多い。すると集中は分断されて本来の集中(塊)の大きさがうまく計算に反映されない。
森下さんは分布の解析を思考して、最初にぶっつかった課題がこれである。その解決の為に個体と個体の間隔を測定して分布形を判定すれば、集中(塊)はそのまま分布形の計算に反映できることになる。
この着想の見事さははじめは何となく理解していたが、私も年齢を重ねるにつれてますますスゴイと思うようになった。1994年の国際生態学会で与えられたDistinguished Statistical Ecologist Awardは後のIΔもさることながらこの着想が評価されたものと私は思っている。
個体の分布が集中的になっているか、あるいは逆にできるだけ互いに相離れた状態になっているか(これを一様型または分散型などとよぶ)、を判断する基準になるのはランダム分布である。計算機で取り出した乱数を二次元で表せばそれがランダム分布である。しかし、当時は北川敏男著「丸善七桁乱数表」以外にランダムの手がかりがなかった。はじめはこの乱数表からグラフ用紙に点を打っていたが数百(面積当たりの密度を変えたりすると数千)の数字を打つのはとても労力がかかった。いまでは丸善乱数表などは古書でも無いのでは、と思うが、この数値表はA4に乱数発生の数式で計算された7桁の数字が7掛け7づつ、びっしりと当時の9ポイント活字で印刷されていた。
あまりに労力がかかるので何か自然界で乱数分布をしているものはないか、これも門前屋での大きな話題であった。雨は天から降ってきた互いにぶっつかるので地面に落ちてくるときにはランダムになるのではないか?こんなことも話題にあがった。森下さんは「調べてみよう」と早速にのってきた。
無風で霧雨が最も望ましい雨だということになった。薄板に白地のケント紙を貼ったものが数枚用意された。曇りの日は朝から研究室につめて雨が降るのをまつ毎日がつづいた。しとしとと降ってきた。理学部玄関前には白い板をもった学生たちが待機していた。ストップウオッチをもった森下さんが「用意」号令をかける。学生たちは板を白い面を下にする。「走れ」という声でそれぞれかってな方向で開けた場所にゆき待機する。「測定」の声で板をひっくり返す。確か5秒だったとおもうが、「止め」の声で再びひっくり返し、大急ぎで研究室に走りかえり、ものも言わずにエンピツで雨滴に×印をつけてゆく。たしか二人一枚で作ったように記憶している。
こうしてできたのが雨滴図(pdf図)である。この図は既に森下さんが計算に使用したので、点の間に線が多数引いてあるが、オリジナルは薄板に貼り付けたグラフ用紙である。300あまりの×印が打ってあった。
同じくpdfに計算過程の森下オリジナルを添付してある。これがいわゆる間隔法と称される計算法で、方形区に代わり個体の間隔を直接にはかり、その頻度分布表とランダム分布のそれと比較する。もしランダムよりも分布表のグラフが有意に右にずれておればその個体群は集中的分布をしており、左ならば一様的分布と判定される(一様的とは個体ができるだけ互いに相離れるように分布する傾向である)。
図を見て頂くと、森下さんは個体間の一番近い間隔を測定することを基本として(最小間隔)、二番目、三番目の間隔も測定して分布形を判定する方法なども考案している(詳しいことは文献欄を参照されたい)。